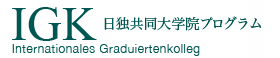セミナー&シンポジウムの記録
08'秋季・共同セミナー参加記②:IGKセミナーの感想
長沢 優子 (総合文化研究科 地域文化研究専攻・IGK所属)
今回のセミナーは、この日独共同大学院プログラム(IGK)が2007年秋に始まってから通算3回目となるものだったが、今年度博士課程に進学した私は初めてこれに参加した。今回は学生のワークショップに重きが置かれ、そこでは小グループに分かれて討論を行った。ハレ側には日本語を学んでいる学生が複数いるので、ドイツ語と日本語の両方を使いながらの議論となった。不自由さを感じながらも自分の考えを伝えようと努力し、また互いに耳を傾け共通の理解を模索する中で、日独の学生間の距離も縮まったように感じた。今回議論したテーマの一つでもあった「国際社会における市民共同体」とは、このような根気ある話し合いと相手を理解しようとする努力によって作られるのではないかと感じた貴重な体験でもあった。またこれまでにドイツ語圏での長期の滞在経験もなくドイツ語をまだ自在に操れるわけではない私は当初言葉の壁を心配していたが、少人数のグループだったので大きな勇気がなくても発言しやすく、積極的にドイツ語で話すことができた。全体会では各グループでの議論の成果を発表し、それをもとに発展的な議論を行った。また日独の大学の先生方による講義やシンポジウムも行われた。 
一方で、欧米で形成された「市民社会」の概念を日本のような欧米諸国とは異なる歴史や文化背景をもつ地域において、しかもドイツ語や英語などの外国語で論じることの難しさも感じた。この問題は次回以降のセミナーで引き続き考えたいと思う。またちょうどこのセミナーの直前に、アメリカで金融危機が発生した。セミナーが行われていた10月初めはその影響の程度はまだ予測できない部分が多かったが、時間とともにその深刻さが増してきているのを見ると、規律を失って暴走し、人々を否応なく巻き込むグローバルな経済や市場の論理に対して、各国の、あるいはトランスナショナルな「市民社会」の良識はどう対処できるのか、喫緊の課題として考えなければならないように思う。
また日程の合間を縫ってハレ大学の先生方との面談の時間を設定して頂き、今後の自分の研究にとって親身で有益な助言を得ることができた。私は次の秋からハレ大学への留学を予定しているが、事前に留学先の大学で先生方との面識を得たり友人を作ったりできるのは、このIGKならではの非常に恵まれたことだと言えるだろう。さらに現在留学中の先輩に寮の部屋を見せてもらったり市街を見て歩いたりして、留学生活を具体的に思い描けるようになった。そのおかげで現在は自分の研究やドイツ語の勉強にもより弾みがつくようになったところである。