セミナー&シンポジウムの記録
11'春季・共同セミナー参加記:市民社会とジェンダー秩序・死刑制度
伊豆田 俊輔 (総合文化研究科 地域文化研究専攻・IGK所属)
1.はじめに2011年3月8日から11日にかけて、日独共同大学院(Internationales Graduiertenkolleg=IGK)春季セミナーが東京大学駒場キャンパスで開催された。 本セミナーでは、市民社会が抱え込む暴力的な秩序(ジェンダー秩序や死刑制度)をテーマとし、日独の研究者による講演、セミナー参加者の研究報告、さらに学生 を主体としたディスカッション(学生ワークショップ)が行われた。報告者はIGKプログラムの枠内で2010年の秋からハレ大学で研究を行っており、一時帰国しセミ ナーに参加した。以下では学生ワークショップを中心に、セミナーの概要を示していきたい。

学生ワークショプは、日独双方のメンバー協働と積極的な参画が求められる作業である。参加者は事前に共通の資料を 各自読み込み、テーマに関する基礎的な知識を共有する。そして当日にはまず研究者・識者の講演が行われ、議論のため の問題提起がなされる。その後参加者が少人数(4-6人程度)のグループを複数作り、1時間程度の討論を行う。最後に全体 討論の場を設け、各グループがそれぞれ議論の成果を発表しあい、さらに互いに質問・リプライをしてゆく形で討論を進行 させてゆく。研究成果を単に並列紹介するのではなく、東京大学とハレ大学の参加者が徹底的に論じあう本ワークショップ は、IGKセミナーの一つの大きな特色といって良いであろう。

第一の学生ワークショップでは、政治学・社会学的観点から、市民社会とジェンダーの問題が取り扱われた。ここではま ずフュステベック氏(ハレ大学)による講演が行われた。議論は以下のようにまとめられる。NGOなどの非国家アクターとし ての「市民社会」の拡大はしばしば、女性の社会進出と両性の同権を推し進めるものとして理解されている。こうした認識 は、ボランティア活動や地域コミュニティーへの女性の参加率が男性に対してより高いことなどによって生じている。しか し、市民社会こそ女性が活躍できる場だと捉える言説は、「国家・対・市民社会」=「公的領域・対・私的領域」=「男性・対・ 女性」という二元的な枠組みに基づいている。そしてこの枠組み自体が、女性を公的な領域から排除する父権的・男性優 位社会を構成する言説に根ざしている。それゆえ、「市民社会の拡大は女性解放につながる」と単純に言祝ぐことはできな いのではないか、というものである。その上で、市民社会は具体的にはどのような場合に両性の同権を促進しうるのか、ま たどのような場合に平等を疎外しうるのかという問いが提示された。
私が参加したグループでは、両性の同権を推し進めるために何が重要かを中心に議論が進められた。そしてここでは教 育や法律、具体的には性差別に対する罰則が必要不可欠であるという意見が出た。こうした制度整備には、市民社会と国 家や政党といった機関との協働や、女性の公的領域への参画が欠かせない。それゆえ、両性の同権を達成するために必 要なことは、前述の講演で指摘された「国家=公=男性・対・市民社会=私=女性」という二分法的な枠組みを解体してゆ く事であるという結論に達した。


引き続いて、近代市民社会とジェンダー秩序の形成について歴史学的な観点を交えた討論が行われた。まず弓削尚 子教授(早稲田大学)が、ナポレオン戦争期のプロイセンの国王夫婦と明治の天皇皇后がメディアで「理想的な男女像」とし て表象されてゆく過程を具体例に分析しつつ、近代市民社会の形成と性差に関する言説が密接に連関していることを論じ た。そして、19世紀前後に定着した性役割の規範意識は、現在の日本とドイツにおいて消滅しているのか、存続している のかという議題が提示された。
第一に論点になったのは、規範の体現するものが、両国において存在しているかということである。現在のドイツでは、政 治家や芸能人が部分的に夫婦・家族関係の「モデル」を示すことはあるものの、基本的に「理想の男女像」を体現する者 はいない。これに対して日本では天皇制度が存続しており、その家族形態はしばしば、国民にとって、家族や夫婦のあり方 の規範であるかのように報道されることも多い。しかし彼らは同時に、戦前から続く「(国民からの)超越性」を備えていること が同時に求められるため、完全には一般の国民の「モデル」にもなり切れない。さらに、どこまで市民が実際に彼らを「モデ ル」と見做しているかは、別の問題として考える必要がある。
しかし意外だったことは、こうした差異にもかかわらず、「19世紀に誕生したジェンダー秩序・規範意識は、大きな変化を受 けつつも、両国において生き残っている」という点でほとんどの参加者の見解が一致したことである。日本ではすでに、男性 が一人で家族を養えるだけの収入を得るのは極めて困難であり、既婚女性の相当数は就業している。このため、性差に基 づく旧来の役割分担は現実的ではなくなっている。それにもかかわらず、「男性は仕事を中心に、女性は家庭・育児を中 心に」という生活形態と規範意識は強固に存続しているのである。これはドイツでも程度の差こそあるが当てはまり、その 原因としては、前述の議論でも出たように、男性の育休取得の困難さや、女性が管理職をめざした場合に発生する負担が 考えられる。
ただし、こうした生活スタイルや価値観は安定しているわけではなく、市民社会の中からたえず揺さぶりがかけられてい る。こうした「揺さぶり」の日本での一例として、討論の中では、男性の育児を支援するNPO活動「イクメンプロジェクト」の存 在が紹介された。この運動は、男性が育児をすることに「男らしく、格好良い」というイメージを付与し、男性の育児参加を促 進してゆくものである。これは既存の「男らしさ」の存在を真正面から批判するのではない。むしろ「男らしさ」の存在を肯定し ながらも、その内容を少しずつ書き換えてゆくという試みである。こうした活動からも伺えるように、性役割分担のイメージは、 市民社会側からの刺激で、今後更に変化してゆくことは間違いないであろう。
セミナー参加者には既婚者や子育てをしながら研究を続けている者も多く、仕事(研究)と家庭生活のバランスの問題は、 学術的な討論対象であるだけではない。むしろ日常に立ち現れる問題である。そのために議論は、歴史的分析と自分たち の日常生活を照らし合わせる作業となり、非常に熱を帯びたものになった。
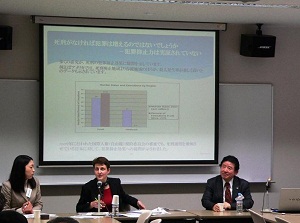
ジェンダーと並び、今回のセミナーの中心的なテーマになったのは、日本の死刑制度である。ここでは死刑廃止運動に携 わっている中村治郎弁護士(日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会副委員長)に参加して頂き討論を行っ た。ディスカッションに先立ち、中村弁護士は日本の死刑制度の現状を紹介し、主として以下5つの理由から、死刑制度の 廃止の必要性を論じた。その理由とは1)死刑は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」にあたる。2)「日本の世論は死刑を支持し ている」とされるが、その「支持」とは、情報が遮断された中での「支持」に過ぎない。3)厳罰化の引き合いに出される「治 安の悪化・凶悪犯罪の増加」は現実には起こっていない。4)誤審の可能性がある。5)国際的には死刑制度は廃止の流れに 向かっている、というものである。そしてグループ討論のために、死刑制度の現状やその存置・廃止、死刑を廃止した場合 の代替刑、遺族感情が主たる論点として提示された。
報告者が参加したグループでは、日本の死刑制度の特徴をドイツの現状と比較することで明らかにし、上記の問題に答え るよう議論を進めた。ドイツでは既に憲法で死刑の廃止が明文化されており、大きな問題として扱われることはない。ただし ハレ大学の参加者からは、「ドイツの世論がつねに死刑廃止を力強く支持しているわけではない。仮にドイツで死刑賛否に 関するアンケートを取れば、どちらが多数を取るかわからないのではないか」という意見が出された。こうした点を考慮する と、日独の死刑問題に対する違いは、世論の支持そのものではなく、ドイツの様に死刑の問題が世論の集団的感情から比 較的独立して決定されているのか、それとも日本のように世論に強く規定される形で進められるのかという点にあると考えら れる。さらに、ドイツでは遺族感情が刑罰そのものの厳しさに酌量されることはほとんどない。日本ではこれに対して、 近年の被害者・遺族の権利や感情の重視が、ほとんどそのまま厳罰化につながっているという差異がみられた。
全体の会合では、「日本では死刑と無期懲役の間に極めて大きな差異があるので、死刑を廃止し、代わりに終身刑を 置くべきではないのか」、「すべての遺族が認めるまで懲役を科す、『半・終身刑』のような制度を導入できないか」など多く の意見が出された。中村弁護士は各グループの発表に熱心に耳を傾けた上で、「日本の無期懲役は執行レベルで厳罰化 が進み、近年は仮出所までの期間が増加し30年近くなっているため、世間一般に思われているほど無期懲役は軽い刑 罰などではない」、さらに「仮釈放を認めない終身刑を導入することは、死刑と同じような残虐な制度になるのではないか」と リプライし、熱心に討論に参加していただいた。このため全体討論も単にグループ作業の結果を報告する場ではなく、異 なった意見がぶつかり合う、実の伴うものになった。

2007年より続いているIGKセミナーは今回で8回目の開催となり、参加者として、熟議をめざす文化が醸成されてきている ように感じた。議論の大半はドイツ語で行われたが、日本側参加者のドイツ語運用能力や、ドイツ側参加者の日本への関心 の高さ、そして双方ができるだけ異なる考えを聞くという意識で臨んだために、闊達に意見を述べあう場が形成できたと考え ている。
しかし、3月11日の14時46分に東北関東大震災が発生し、セミナーは最終日の前半までで打ち切られることとなった。こ れに伴い、これまでの討論成果を締めくくる全体会合や、セミナーのハイライトとして準備が進められていたシンポジウム 「市民社会と暴力」も急遽中止が決まった。それまでの議論を総括する機会が失われたのは残念でならない。しかしなが ら、震度5強の地震と都市交通のマヒにもかかわらず、幸いにも参加者に一人の怪我人を出さず、混乱も生じなかった。 今回の地震は第二次大戦後、最悪の規模の自然災害となり、本報告を書いている現在(4月)になっても、死者・行方不明 者の総数は杳として知れないままである。さらに福島第一原発に関しては、廃炉への具体的な工程はもとより、当面の事 態収拾の目途すらついていない。報告者は4月からハレでの研究生活を再開しているが、災害の大きさのためか、未だに 日常に復帰したという感覚がない。
しかし、ハレ大学は早くもこの地震に対する募金活動や、日本の市民社会と自然災害、原子力政策についての議論を始め ている。研究者としてどのような形で有用な知見を提起できるのか、また市民としていかにこの問題に貢献できるのか、非常 に重い課題が渡されていると感じている。


